日本茶も紅茶も中国茶も。
♪冷めてしまったチャイニーズ・ティー、お前の好きだったチャイニーズ・ティー
…泣かないで〜(ねちっこく)泣かないで〜(ねちっこく)♪
因みに→「泣かないで」(うたまっぷより)
関連項目→お茶会つながり、→珈琲つながり▼シナの茶全部。
 『シナの茶全部』(R・ブレットナー) 『シナの茶全部』(R・ブレットナー)
※「年刊SF傑作選2 創元推理文庫SF」の収録作

シナ茶は昔、大変高価だったわけで、
その比喩として、「シナの茶全部もらっても、イヤだね!」と少年が悪態をつくところから始まる印象的な短篇です。
全然SFではなくて、ファンタジックな奇妙な話だと思いますね。SF嫌いにもオススメできるファンタジック・アンソロジー。
特にこの年刊SF傑作選2には、ロバート・F・ヤングの『たんぽぽ娘』が収録されているのが肝です。他の作品もなかなかそそられる、ジュディス・メリルの名編集。たいていの場合、他巻は価格抑え目ですので、揃えたい。
→ミニ特集・名アンソロジー
→ミニ特集・たんぽぽ娘
▼茶の葉。
 『茶の葉』(E・ジェプスン、R・ユーステス) 『茶の葉』(E・ジェプスン、R・ユーステス)
※「世界短編傑作集3 創元推理文庫」の収録作

死体の刺し傷のところに茶の葉が付いていた。
そこから推理する密室殺人。短編です。
ネタバレするので、詳しくは語りませんが、
今や万人の知るトリックでは? 古典中の古典ですよねー。
→世界短編傑作集についてはコチラ
▼持っていたいね。
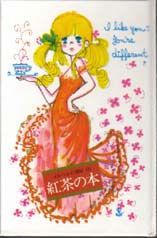 『メルヘンの部屋18「紅茶の本」(世界の詩とメルヘン18のセットより)』 『メルヘンの部屋18「紅茶の本」(世界の詩とメルヘン18のセットより)』
(里吉しげみ&水森亜土/世界文化社)

スゲーかわいーです。
亜土ちゃんのカラーイラスト満載、キュートな紅茶のウンチク本。
見過ごせないシリーズの中の特に見過ごせない1冊。
→ミニ特集・メルヘンの部屋
▼ヒナギクのお茶。
 『ヒナギクのお茶の場合』 『ヒナギクのお茶の場合』
(多和田葉子/新潮社)

短編集です。
表題作は作家の「わたし」と、舞台美術を職業にするハンナのお話。
わたしはウイキョウとヒナギクのお茶の使用済みティーバッグをハンナのために残しておく。
ハンナが紙を染めるのに使うから。
「それから、ティーバッグというものも、使い終わったら捨ててしまうものだと、思い込んでいた。思い込んでいたことが多すぎる。ハンナに出会うまで(本文より引用)」
多和田葉子さんの作品を読むのは初めてです。
豊かな感性と漂う思索、それがそのまま文章になっているようです。
膝を打ちたくなる箇所がいくつもありました。
私はこの小説のラストが好き。
推理小説風に言わせていただくと、途中にさりげない著者のミスリードが紛れていて、
まんまとしてやられました。これ、わざとですよね?
声に出して笑うような小説ではありませんが、ただ愉しめばいいのだと思います。
→菊つながり
▼紅茶。
 『続・紅茶の時間』 『続・紅茶の時間』
(東君平/サンリオ)
詩集です。
帯は「あなたの心のティータイム」。
巧いですね!
小さな恋の香りのする詩と、ニッコリするような小さな真実のある詩。
そんな詩集です。
構えずに読む。企みなく読む。そういう時間も必要です。
「紅茶の時間」
木蔭のテーブル
紅茶に うかんだ
レモンの 薄切り
こんな小島に
ふたりで住みたい
(本文より)
私は意外に アトガキが好きです。
その一節。
アヒルガ イタラ
ナキマネ シヨウ
クサガ アッタラ
クサブエ フコウ
カラスガ ナイタラ
モウ カエロウ
(アトガキより引用)
そんな人に私はなりたい。
※流通中(現在定価¥795)
▼紅茶。
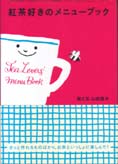 『紅茶好きのメニューブック』 『紅茶好きのメニューブック』
(山田詩子/文化出版局)

紅茶に合うレシピ集です。
めざめのティー、朝食のティー、イレブンジズ、お昼ごはんのティー、ひとやすみのティー、おもてなしのティー、夕食のティー、おやすみ前のティー、
それぞれに合う軽食やお食事のレシピ。いろんなティーの入れ方もあります。
写真は一枚もありません。著者の山田詩子さんは紅茶の店「カレルチャペック」を開店した方。というわけで、おなじみのかわいい絵が挿絵になっています。
レシピは簡単で、すごーくおいしそうです。
小さなはちみつパン、簡単りんごケーキ、バナナのパン、豆のカレー…。
▼とにかく日本茶。
  『暮しの茶 平凡社カラー新書26』 『暮しの茶 平凡社カラー新書26』
(小川八重子/平凡社)

保育社のカラーブックスか、平凡社カラー新書か。
古本好きは一度は考えたことのある二択ではないでしょうか。
カラーブックスと同じく、写真ふんだんな丁寧な作りで、
テーマの幅の広げ方、掘り下げ方もお手のもの。
ただ、カラーブックスよりテーマ選びがひねってある気がします。
どうでしょう?
本書では、日本の暮しに密着する「茶」を、いろいろな側面から見つめ直しています。
▼他に…『オリビアを聴きながら』
|